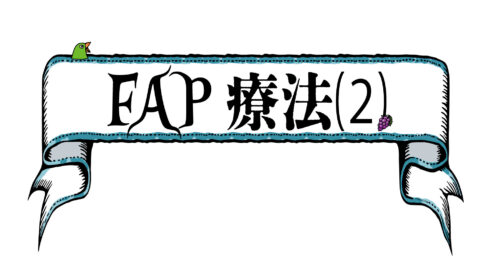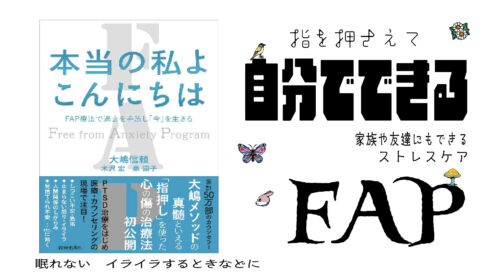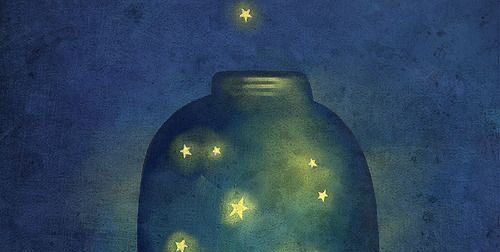FAP療法(Free from Anxiety Program)は、2001年に大嶋信頼氏らによって体系化された心理療法です。治療にほとんど苦痛を伴わず、また過去の苦しい体験を治療者に語らずとも介入できることが特徴です。
何度も繰り返される不快な出来事、過去の不快な記憶、中々消えない不快な身体感覚などに対して、指(臓器反応など)などを用いて不快なことが想起されている瞬間の生体の動きを捉え身体的に共感します。
現代催眠等の要素も用いながら、その人の持つ生理的なバイオリズムを活かし本人にとって自然な形で、危機的状況があったときに脳内で統率されなかった情報処理や活性のアンバランスさが再統合されるのではないかという仮説に基づいて、構築されています。
バラバラに反応していた電気信号が統率されることで、繰り返される行動や、思考、不快な現実が膠着している状態が自然と変化していくのではないかと考えられています。
詳しくはインサイトカウンセリングさんのHPをご覧ください
身体の感覚に共感…などと言われるとギョッとするかもしれませんが、例えばAさんに緊張するがBさんに緊張しないという状況があるとします。
対人緊張が全人類に適応されるのであれば、AさんにもBさんにも対面した時等しく緊張するはずです。
しかしAさんとの間にのみその状況が現れるということは自分にも、相手にも、そこに非言語的にやりとりされる“状態“があります。これはカウンセラーとクライアント間でも起こり得ることで、お互いのそういったものを手がかりに共感していきます。
実施方法の推移
初期は指を抑えるという方法で治療を行なっていたそうです。(手順は本当のわたしよこんにちはに詳細が記載されています。)
指刺激で扁桃体に刺激を送り、左右に意識を動かすという行程で海馬に対しても刺激を与えさらに扁桃体との繋がりを持たせます。そして再度扁桃体を刺激することで、心的外傷体験と感情が統合されると考え構成されています。
そこから手順の更新が進み、初期にはクライアントさんも一緒に発声してもらう必要があったのが現在は治療者が指を振り、クライアントさんは目を閉じてただその言葉を聞いているだけでよく、負担がより少なくなっています。
どんなことをするの?
主訴をお聞きして、治療者が指を振ります。反応が出たコード(呪文のようなものから生理学的なものまで)をクライアントさんは目を閉じ頭の中で唱え続けます。途中で唱えるのを忘れてしまっても大丈夫です。
これを何ターンも繰り返していきます。コードが事実、と考えるよりはその反応の出たコードが、悩みやクライアントさんにとって解放されるナラティブとなるという捉え方で問題ないと思います。
例えば緊張という言葉を想起すると緊張していた時の体の感覚や場面の記憶を脳は探り出します。そうした言葉によって想起される体の感覚を、指の反応(感情含む臓器反応)を用いて整理していくイメージです。
また、例えばSAの問題などを直接SAをコードに治療を進めていくときもあれば、全然関係ない悩みやコードを繰り返すうちに、意図せずその部分が少しずつ良くなっていく様子なども度々お見かけします。
これは他の心理療法にも言えることだと思いますが、このように一見自分の苦しみと直接的な関係がないように思えるような方策のアプローチでも幅広い範囲に影響を与えることがあります。
無意識は奇妙で、いつも思いがけない方向からやってきて、思いがけないところが繋がっていたりします。
どのように効果を感じるの?
PTSDの程度によっては明確に変化を感じることがあります。日常のお悩みなどは本人にとっては穏やかに感じる変化を醸し出すことがあります。
たとえば、
- 悩みが最近少なくなった・よく眠れるようになった・出かけることが増えた(もしくは減った)
- 相手の態度が柔らかくなった・対象の人と会うのが楽しくなった、もしくは興味がなくなった・パートナーや家族のの調子が良くなった
- 何もしていないのにお客さんが増えた、などと認識することもあります。また、悩みを思い出せなくなる方などもいらっしゃるようです。
- 他人がクライアントさんのことを変わったなと認識したり、逆に相手が変わったなどと認識することも。
- 本人には自覚があまりなく、なぜか最近ラッキーになった。調子が良いなどとおっしゃられる方もお見かけします。
- また物理的に疲労が取れてきて、仕事が早く終わるようになったなども感想としてお聞きします。
ミラーニューロンのことを前提に考えると、こちらの脳の帯電、抵抗や不安感が消失するなどその他様々な要因から間接的に非言語的情報が伝わる事でそのような事が起こりうる一因となったり、自分の素の感覚と繋がりやすくなったからとも取れるのかもしれません。
ナラティブ・アプローチ
FAP療法にはナラティブ・セラピーが組み込まれています。ナラティブとは1900年代後半に社会構成主義の流れを汲んだ治療家たちが家族療法を実践する中で編み出されていきました。その中で療法家たちは治療者をどこのポジションに置くか?という問いにぶつかりました。
家族療法ではセラピストも家族とチームになって参加しますが、そこで客観的な観察者として振る舞うという立場をとっていました。
そうすれば巻き込まれず毅然と接触できているように感じるけれど、家族側からは学説を私たちに当てはめようとしているように感じるとか、語りを観察されるけれど尊重されているように感じられず、もっと娘の話に耳を傾けてくださいなどの感想が出たりしました。
治療者側でも、毅然と接するということは暗黙のうちに、治療者たちがクライアントのことをよく知っていて、更に進むべき道をも知っていると態度で示してしまうようなものだという声が上がったりしました。
そうやってクライアントの語りをどう聞くかといことを模索していく時期があり、それらの課題を背景に心理学の分野で発展していったのがナラティブセラピーです。
医療の分野ではEBN(Evidence-Based Medicine)とNBM(Narrative-Based Medicine)があり、EBMが科学的な根拠を重視する一方、NBMは患者の視点や背景を考慮し、よりパーソナライズされたケアを目指すという定義があります
私はその人の症状や身体、年齢や生活など様々なことを一つ一つ分断せずに、全人的1に捉えるという考え方が好きです。また状況として問題が存在しているように感じたとしても、それはその人の生命や存在が問題であるわけでは全くないという視点が好きです。
そして、症状や問題に見えるものも反転させて見ると、自分や自分の人生や命を守るために発生していた現れだったのだと認識することもあります。
されど人間は突拍子もなく病気になることもあります。その時病気の私と捉えるか、病気を持った私と捉えるか、病気によって失ったけれど得たものもあると捉えるか、などその捉え方は一人によって異なり、人の数だけ何億通りと存在します。
その捉え方が自分を追い込み蝕むストーリーでなく、一つ一つの物語の欠片たちを集めて、自分を責めない内側から現れる自然なストーリーに統合されれば、驚異的な苦痛から解放されて安寧に生命が保たれ歩みが再開するかもしれない。
しかし、そこに行くまでには物凄く労力や体力や痛みがあり、また逆境の中を生き抜いてきている人たちにとっての”それ”は大きすぎて、統合し直す際に直面化するのはあまりに大きなものだったりします。
ではどうやって紐解いていくのか?
SVを受けながら何パターンかの見立てを立てますが、最後は指の反応で大方の方針を決めていきます。
それがセッション中双方が無意識状態で治療に入れて、治療者側の万能感や思い込みを外すというプロセスとして秀逸だなと感じています。
FAP療法は、いろいろな部分に対して軽やかにアプローチできて、またセラピストが誘導することなくその方の内側にある力や無意識の力を使えるようシステム化されている療法です。
ナラティブアプローチがどう組み込まれているのか?また続けてブログに書いていきたいと思います。
ナラティブとは☁️先生のコラム記事
ナラティブとは☁️Wikipedia
社会構成主義:社会の中で認識される現実は客観的な事実ではなく、複数の人間が持ち寄る解釈や認識によって意味付けられ作り出されるものとみなす考え方。人種による文化や物事の認識、政治や社会構造によって共有されるイメージが人々で共有されて生み出される文脈(現実)は異なってくると考える。立つところにより現実の見方は変化する 心に焦点を置き内省を加え心理学化が行われた 対義語:本質主義
家族療法:個人の内部に問題を見出すのではなく家族という単位で観察し、家族全体の歪みや危機が起こっていると考えます。全体の問題を表出する役割として、一部に歪みが出てくると捉え直します。親たちもまたもっと上の家族の単位から問題を引き継いでいることが見えてくることもあります。また結婚などで構成メンバーが変わることでバランスが変わり、家族の危機や問題が自然と消滅する様子などが見られたりします。要ケアが必要な人が家族にいる場面などで、どこかにそれを支える役割が偏るとそこで新たな問題が生まれ、直接ケアに加担していないその子供もバランスを崩したりすることが見られます。個人の特性や家族全体のリソースを活かし、役割分担を組み直したり、時に家族の単位(構成メンバー)を広げたりすることで、そのバランスによって問題を考えていこうという考え方です。
- 英国医師シシリー・ソンダースが末期がん患者との関わりを通して提唱 1.身体的苦痛 2.
精神的苦痛 3.社会的苦痛 4.スピリチュアルペインから全人的苦痛が構成されているという概念 ↩︎